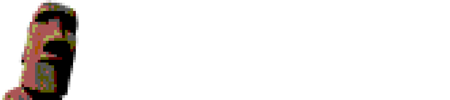過去の遺産というか、今から7〜8年くらい前に別所で投稿していたブックレビュー的なものの残骸をあわよくば本ブログの水増しになるかと思い再構成したものとなります。自分としては結構な本数を書いてたような気がしてたんですが、気付けば我ながらガッカリするほど少なかったですね……。
なお、少々文体が砕け気味というか、むしろ砕け散ってしまってる箇所なども散見されますが、(今よりは)若気の至りと寛大な気持ちでご容赦下さればと。
喜嶋先生の静かな世界
※内容に関する記述を含むため、ネタバレ注意
学園ドラマならぬ学問ドラマ小説。
そのスジに縁の薄い当方にとっては、ある種異世界のファンタジー小説を読んでるような気分にさせられるんだが、かつてそういう世界にどっぷりと浸かっていた、あるいは現在進行形で浸かっている人にとっては、思わずニヤリとするか苦笑いしてしまうような内容なんだろう、きっと、多分。そういや現在進行形である(はずの)知人Y.H氏は、異世界でうまいことやってるんだろうか。
さて、この作品、途中までは抜群に面白いんだけど、ラスト数ページの後味の悪さといったらもう・・・・・・。冗談抜きで読後しばらく放心状態だったわ。
著者の自伝的小説とのことだが、これってどっからどこまでがフィクションなんだろうか?
もし殆ど事実そのままってんなら、現実という名の絶望に打ちひしがれること請け合いの切なさだわ。
とは言え、先にも述べた通り(概ね)引き込まれるような面白さを持ち、加えて文中には思わず感心させられてしまうほどの台詞や語録などが随所にちりばめられ、小説ながらにひょっとしたら今後自身の人生指針となり得る珠玉の名言が見つかるかもしれない、まさに二度おいしい良書であると感じた。
「アンハッピーエンド?オッケーオッケー!自分、悲劇耐性高いんで!!」
って人にはひとまずお勧めしておく。
しかしなぁ、あのラストはなぁ・・・・・・浮かばれんなぁ・・・・・・。
嫌な女
なんとも不思議な小説だ。
おもなあらすじとしては、対象的な二人の女性、女詐欺師の小谷夏子とその遠縁にあたる女弁護士の石田徹子との奇妙な関係が織りなす人生模様を主軸としている。
これがハリウッド映画とかなら、さんざん小悪事(?)を働いてきた夏子がふとしたきっかけで巨悪に捕えられ、これを徹子が弁護士として敏腕を奮い窮地を切り抜け、最後に夏子は涙を流して改心する、といったような、いかにもありがちな流れになりそうなものだが、幸いな事に本作はそのような展開とは一切無縁である。
あくまでも話は淡々と進み、決して読み進める毎にグイグイと惹きつけられるような息もつかせぬストーリー展開ではない。
小説のタイトル通り、女詐欺師は最後までやっぱり嫌な女のままだし、今あらためて振り返ってみるに、果たしてこの小説の山場とは一体どこであったのだろうかという疑問すら浮かぶほどに、さしたる抑揚のないままに話は進んでいく。
このように書くと、果たして本作は取るに足らぬ駄作であったのかと思いがちであるが、その問いに対しては声を大にして「否」と答えざるを得ない。
たしかに、息もつかせぬような派手な展開も「してやられた!」と臍をかむような意外などんでん返しもない。
しかしながら、読み進めていくうちに思わず目頭が熱くなる場面も何度かあり、読後には清々しい感動を覚える良作である。
もしも機会があれば、是非一度読んでみて欲しい。
Lady,Go
先に読んだ「嫌な女」とはうって変わって、こちらは直球どストライクな構成の作品。
それはもう、あらすじもつぶやきレベルで説明できるほどに!
(例)地味な女主人公がキャバクラ勤めを通し成長し、夢を実現させるサクセスストーリー(38文字)
ありきたりと言えばありきたりな内容ではあるが、そこはさすが売れっ子作家の手腕で全編を通して無難にまとまっており、読後「俺の時間返せ!」という失望感につつまれるようなことはない。
ただし、「いやおん!」(※嫌な女のことです)並みのクオリティを求めて本作を手にした場合、やや肩透かしを食らうかもしれない。うわぁ何かエラそう。
以下、気になった点をいくつか。
作中、主人公視点のモノローグがところどころに入るのだが、これが敢えて意識的にやってるんだと分かってはいるものの、その部分だけ文章が突出して拙すぎるため思わず「ケータイ小説かよ!」と突っ込みたくなる。あと「もぅマジ無理」シリーズを思い出して吹く。
さらに言うなら、いささか女主人公が何も知らなすぎる感が否めない。
いくらなんでも24歳で社会人までしてて、「気品」の意味が分からないってこたぁないんでないか。
仮に、辞書に書かれているような抽象化した内容で説明できないってことだとしても、とある人が気品があるかないかの判断くらいはつくんじゃないスかねぇ・・・。
以下は余談となるが、本作の発表は2006年。著者の出世作となった「県庁の星」に続く作品として刊行されている。当時の我が身を振り返れば、奇しくも作品の舞台となるキャバクラという世界を少なからず垣間見て・・・いや、もうぬかるみに片足ぐらいは浸かっていたかもしらん(カモネギ的な意味で)
もし、あの頃に発売間もない同作品に出会っていたなら、キャバクラという「舞台」を客観的に見つめ直すきっかけを得ることで、あるいは今とは少しばかり違った人生を歩んでいたかもしれぬなぁなどと、いささか感傷的な読後感に浸ってみたりした。(『黒い太陽』読んでもきっかけを得られなかったヤツが何を今さら・・・)
思い返せば当時、気品はなかったなぁ。
なに?
今もないだろって!?
うるせぇコノヤローーー!!(←やっぱりない)
明日この手を放しても
これまた難しいテーマに取り組んだ作品すなぁ。
本作の主人公は兄、真司と妹の凜子。凜子は途中失明により視覚障害者となる。
しかし、一家を襲った不幸はそれだけに留まらない。
ほどなく家族の中心的存在であった母親が他界し、さらには父親も突然失踪するという三重苦。
残された兄妹の運命や如何に―
序盤でそんな筋書きを見せられれば、以降さぞかし陰鬱な物語が展開するのかと思いきや、意外にもそういったトーンは感じられぬまま、とは言えノー天気で底抜けに明るく、などという事も勿論なく話は進んでいく。
物語は真司と凜子の身の回りに起こる様々な出来事を通し、徐々にお互いの心情が変化していく様を主軸として書かれているが、この辺りの運びはさすがに手慣れてるなぁと感心する。
や、この真司ってのが序盤ではホントやなヤツなんスよ。
自己チューで短絡的で、何かと文句ばっかり垂れてて、我が身を省みない。もうね、いけ好かないヤツの見本みたいなキャラ。
妹の方も少しばかりめんどくさい性格だったりはするんだけど、それを差し引いても何ともお気の毒な兄をお持ちですねと同情せざるを得ないほどに。
それが、物語を読み進めていくうちに、「あれ?実は意外といい奴なんじゃ?」と思い始めて、とうとう終盤には真司の口から出てくる文句や罵声の台詞ひとつひとつが、作中の凜子が感じたのと同様、心が和むような気持ちで受け止められるようになってしまう辺り、まんまと作者の術中に嵌ってしまったと言わざるを得ない。
ただなぁ、ラストがなぁ。あまりにもあっさりし過ぎな気がする。父親の件も回収してないし。
さて、主人公が障害者であることから、やはり本作で避けては通れない命題として、「健常者と障害者の関係性」があげられるだろう。
こちらについては、随所で作者なりの見解を示しているように思われるが、当方が一番印象的だったのは、真司の勤める会社の後輩、田中とのやり取りの場面である。
真意は不明だが、田中はさして悪気はなく、先輩に対しねぎらいを示したつもりなのであろう。
しかし、当の真司にとってそれは鋭い刃となり心に深く突き刺さり、さらには本人だけではなく自分の家族すら傷付けられたように感じ、激しい怒りを覚えたのだ。
あくまで小説の中の話ではあるが、実際のところ、前述したような摩擦は現実社会に於いても往々にして起こっている事象なのではなかろうか?
そう感じずにはいられなかった。
かつて、ヘレン・ケラーは言った。「障害は不便ですが、不幸ではありません。」と。強さを感じる言葉である。
しかし、全ての「不便」を強いられる人達がそんなに強いわけではないのだろう。
普段「不便」を感じない健常者たる我々が、そのような人達と関わりを持つに至った際、果たしてどう接するべきなのか?
自分の中で答えは未だ見出せていないが、少なからず考えるきっかけを与えてくれた作品である。
いとみち
以前読んだ「陽だまり~」の展開の突飛さに思わず毒づきまくってた当方の批評とは裏腹に、何ですか、やれ文庫本100万部突破だの、映画の観客動員数が半端ない数だのと逆行する世間様のこの流れは!
・・・・・・え、映画の方はほら、主演が松潤やし、ジャニーズの後押しによる効果やから!(震え声&白目)
ここは一つ(よせばいいのに)著者の別作品を読んで事の真意を確かめねばなるまい!これは必然なのだ!
と、いったわけで、前作の売れ行きに気をよくした新潮社より2匹目のドジョウ(※1)よろしく同作者の文庫本化第二弾となる「いとみち」先日発刊されたため、今回こちらを読んでみることにした次第である。まんまと新潮社の策に嵌った感がぬぐえなくもないが、この際それは置いておくこととする。
さて、気を取り直してあらすじをば。
津軽訛りがひどく、それがコンプレックスとなって極度の引っ込み思案である女子高生「いと」が、何とかその性格を克服したいと一念発起して始めたメイド喫茶でのバイトを通じて、人として成長していく様を描いた青春ストーリー。
あれ?なんかデジャブ?
つい最近、ちょうどそんな感じの小説をレビューしたような気が・・・・・・と思ったら、何だ「Lady,GO」かよ。うん、舞台は違えど、正直コンセプトというかプロットはそんなに変わらない、いわゆるお決まりの設定であることはもう否定のしようがない。こうなると、あとはいかに登場人物のキャラクターが独創的であるかだとか、あるいはストーリー展開が絶妙であるか等で差別化をはかるしかないわけだが、それらについては一応、一定の水準は満たしているものと思われる。
ただ、キャラ設定についてはややあざといというか、狙いすぎというか・・・・・・そこはかとなくラノベ臭が漏れ漂ってくる突飛さがありつつも、そのくせどっかで見たようなテンプレ感が透けて見えるようでもある。中でもひっでぇなぁと思ったのは、祖母ハツヱに対する設定である。何でも極ネイティブな津軽弁スピーカーとのことなのだが、その表現手法として台詞が全部意味不明の記号扱い(※2)ってのは一般向けレーベルではいささか悪ノリが過ぎる。(※3)そもそも津軽弁自体、つど解説が必要なくらい独特の言語体系を持った方言なんだから、別にそのままの表記でいいだろと。
一方のストーリーについては、前作のように突如まさかのファンタジー路線へ突入することもなく、あくまで全てはリアルな現実社会上での出来事として進行していく(前回の件があるので、それだけでも高評価というのはやや甘やかし過ぎか)てか、もし今回も懲りることなく陽だまり同様の展開になってたとしたら、有無を言わさずこの本を焚書処分にしたけどね!間違いなく!!
で、展開そのものは・・・・・・まぁ、無難というか、ベタというか。大体先は読める。親バレしかり、店を襲う危機しかり、弦切れしかり。ひょっとして定型パターンなのこれ?ってぐらい全てが予定調和で進行し、ある意味、水戸黄門を観てるような抜群の安定感(※4)を感じる。
これは是非読んで欲しいと猛烈にプッシュするほど突出して面白い訳でもないが、かといって大きくハズレということもない。むしろベタなりにそこそこ面白い。先に述べた、「一定の水準」とは、つまりそういうことだ。
何か褒めてる要素が極端に少ない(てか殆ど無い)ようだが、そ、そんなことないッスよ!例えば、タイトルがダブルミーニングだったり、所々笑える場面があったり、ちゃんと推敲されてるのコレ?って突っ込みたくなる箇所(※5)があったりとか、とか!(いや、最後のは褒めてねぇから)
青春群像劇を生温かい目で見守ることの出来る御仁であれば、まぁ読んでみてもいいんじゃないッスかねぇ。続編も単行本では刊行されてる(※6)みたいだし。
なお、余談であるが、どうせ映画化するんだったら「陽だま~」なんぞより、こっちの方がよっぽど娯楽作品として適切だったんではなかろうかと思わずにいられない。ひょっとして、作中にこれと言った男性キャラがいないので、ジャニタレを起用する余地がなかったから企画ボツったのかッ!?
【注釈】
(※1)
「陽だまり~」の単行本発売は2008年4月だが、こちらは出版業界としては控えめの初版五千部であり、しかもその後重版されることもなくひっそりと市場から消えていったかに見えた。しかし、2011年6月に文庫版が刊行され、以後、爆発的な売れ行きを見せたのはこちらである。一方、今回文庫化された「いとみち」についても単行本自体は2011年8月にすでに出版済みであり、今このタイミングでの文庫本発刊は明らかに(以下略)
(※2)
ご丁寧にも巻末に「ハツヱ50音表」なるものが掲載されている始末・・・・・・って、だれがいちいち解読するかこんなの!
(※3)
MF文庫Jやハヤカワ文庫ではわりと一般的にあるノリ
(※4)
何でも各イベントのタイムテーブルがあらかじめ決まってるとかどうとか・・・・・・
(※5)
「店長の男性だった」とか、「スウェットの部屋着に着替えて~」とか、何か言い回しにちょっと違和感を覚えるんだがこういうもんなの?
(※6)
二の糸が文庫本化されるかどうかは、本作の売れ行き次第か?
いとみち 二の糸
けっきょく読んだ。
さて、内容を一言で言えば、きわめて正統派の、続編のお手本みたいな作品である。二作目ということもあり、舞台設定も定着化し各キャラクターの個性もより明確になったためか、前作よりも書き慣れた感はある。初々しい恋バナを予感させる新キャラの投入に加え、個々のレギュラーキャラについても、より深いエピソードが記され、前作に思い入れがある人ならば物語への感情移入の度合いも増すことであろう。本作を通して、過ぎ去りし淡い青春時代を追体験したいと思われる方は読めばよろしいかと。
さて、こっからダメ出しな。
まず、メイド長の元ダンナのキャラ設定が100%天然果汁テンプレ通りのDQNクズッぷり。ベタって枠を通り越すぐらい余りにもテンプレに沿い過ぎてて、ひょっとしてこれは物書きとしてのプライドを捨て、締め切り優先にひた走ってしまったのではないのかと邪推するほどだ。もうホント、「これティッシュペーパーか何か?」ってくらいあまりにもペラッペラで実に白ける(ティッシュだけに)そのせいで、サブキャラクターとしてわりかし重要なポジションであるはずのメイド長さえ、DQN元ダンナに引きずられてなんだかやたらと薄っぺらな存在になってしまったように感じた。
さらには、物語の山場とも繋がる文字通り元ダンナとの腐れ縁が、きわめてご都合主義に万事解決してしまう辺り、ペラさ加減にさらに拍車をかけている。あくまでライトな青春小説というスタンスを貫き通すというのであればそれでもいいのかもしれんが、こと現実社会に於いてこういう厄介な人種と係わりを持ってしまった場合、そう簡単に話がまとまるもんでもなかろうに。例えば代償として何か大切なモノを失いつつも、それによって店長と娘への愛の深さを再認識するだとか・・・・・・まぁ、そこまでヘビーでなくても、せめて読者に「ご都合主義だなぁ」と思われるような安直な結びをすんなよと苦言を呈したい。
と、書いてはみたものの、よくよく考えてみると、巷に溢れる刑事ドラマなんかも大概そんなモンなのかなぁなどと思い直してみたりもした。あまりにも記憶力抜群な目撃者の証言とか、序盤で殺されるテンプレDQNとか、クライマックスで語られるお涙頂戴の事件に至った動機とか。そんな大量生産の波に乗っかった紋切り型のドラマがいつの時代も巷に溢れてるのは、それなりに需要があるからなんですかねぇ。
何やらえらく批判的なことばっかり書いてきたが、とりあえず本作が青春娯楽小説としては一定水準以上のクオリティを保ち、無難にまとまった作品であることは最後に追記しておく。
だから、「陽だ~」なんかより、よっぽどこっちを映画化すればと何度も(以下略)
サブカルで食う
タイトルから察するに、いかにも実用書的な中身を想像しがちであるが、どちらかというと自身の半生を綴ったエッセイといった色合いが濃い。
全体として軽妙な語り口で、かつページ構成の1/4は注釈欄で構成されているため、おおよそ一時間もあれば読み終えるであろう。
本書で述べる事柄を実生活に活用できるかはともかくとして、著者の筋少時代をリアルタイムで知る(加えて、少なからず当人への興味を抱いた)世代ならば、読んでいて色々と感慨深い内容ではある。
読後に彼らの代表曲をあらためて聴き直してみると、歌詞に込められた意味に新たな発見があるかもしれない。
なお、文中にある「小説の書き方」の下りで、ラブコメの書式(※1)を簡潔明瞭に言及してる箇所は、読んでて「あぁ、そうだよなぁ」と妙に納得してしまった。
(※1)
・ちょっと変わった形での出会い(起)
・どうもお互い好きになったらしい(承)
・でもケンカをしてしまい別れてしまう(転)
・やっぱり復縁してめでたしめでたし(結)